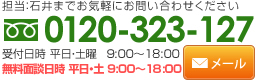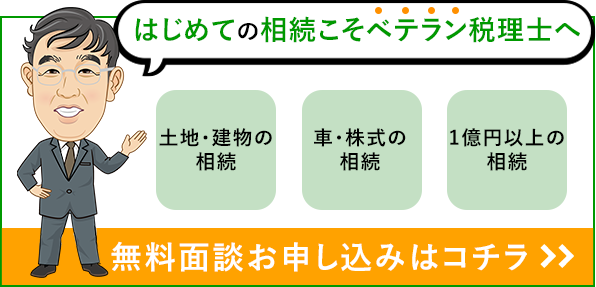souzoku-station
souzoku-station
「子どもの将来のために、少しずつ現金を渡しておきたい」「手渡しなら記録が残らないから、税務署にもバレないのではないか」とお考えの方もいるかもしれません。ですが、現金の手渡しであっても、将来的に税務署に把握される可能性は十分にあります。
なぜなら、税務署は独自のネットワークや強力な調査権限を持っており、過去の入出金記録から「不自然なお金の動き」を見逃さないからです。そこで本記事では、手渡しの贈与がなぜ把握されるのか、後々のトラブルを防ぐためにはどのように贈与を行えばよいのかについて分かりやすく解説します。
【結論】生前贈与を「現金手渡し」で渡すとバレる?バレない?
「家の中でのやり取りなら記録に残らないはずだ」と考える方は少なくありませんが、残念ながらそうとも言い切れません。そこでまず、バレるかどうかの判断基準となる「時間軸」と「きっかけ」について整理しておきましょう。
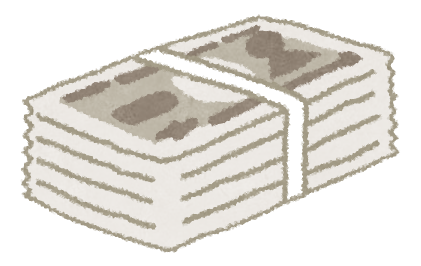
贈与の時点ですぐにバレることは少ないが、リスクは消えない
数万円程度の現金を自宅で手渡しただけであれば、その瞬間に税務署が察知して調査に来ることはまずありません。銀行振込のようにリアルタイムで記録が残るわけではないため、贈与の現場を直接確認されることはないからです。
しかし、これは「バレていない」のではなく、単に「まだ見つかっていない」だけの状態です。これが繰り返されれば、後の資産移動の矛盾として、リスクが積み重なっていくことになります。
「相続」が発生したタイミングで芋づる式に判明する
手渡しの贈与が明るみに出る最も多いきっかけは、将来、贈与者が亡くなった際の「相続税調査」です。税務署は、亡くなった方の過去10年分ほどの預金口座の動きを詳細に調査し、その使い道が不明なケースを徹底的に洗い出します。
一方で、受け取った側の親族の預金が不自然に増えていたり、高額な買い物をしていたりすれば、その差額が「隠れた贈与」として指摘されるわけです。このように、生前贈与を現金手渡しで行ったとしても、かなりの確率で税務署にバレると考えておいて間違いないでしょう。
税務署はどうやって「手渡しの贈与」を把握するのか?

では、税務署はなぜ、目に見えないはずの現金の動きを把握できるのでしょうか?その背景には、個人の所得と資産を紐付ける高度な管理システムと、銀行をも上回る強力な調査権限があります。
KSK(国税総合管理システム)による資産と収支の監視
税務署は「KSK(国税総合管理システム)」を活用し、全国の納税者の所得、確定申告の内容、不動産の売買履歴などをデータ化して管理しています。このシステムにより、個人のこれまでの年収から推定される「本来あるべき資産額」が簡単に算出できるため、実際の相続財産がそれよりも不自然に少ない場合、「どこかへ資産が流出している」とアラートが鳴る仕組みとなっています。
親族全員の口座にまで及ぶ強力な反面調査
相続税の調査では、税務署の権限は亡くなった本人だけでなく、その配偶者、子ども、さらには孫の口座にまで及びます。本人の口座から100万円が引き出された同時期に、子どもの口座に100万円が預け入れられていれば、たとえ手渡しであっても贈与の実態は明白です。
また、口座に入れず「タンス預金」にしていたとしても、後の不動産購入や住宅ローン繰り上げ返済などの資金源を説明できなければ、過去の贈与が露呈することになります。
現金手渡しの贈与でトラブルになりやすいケース
現金手渡しによる贈与は、単に「税金」の問題だけでなく、法的なリスクや家族間の争いを引き起こす大きな要因となります。ここでは、実務上で特に問題になりやすい2つのケースを深掘りします。
①「名義預金」とみなされ、相続税の対象になるケース
「手渡しした現金を子ども名義の口座に入金する」という行為は、最も「名義預金」と判定されやすい典型例です。たとえ通帳を子どもに渡していても、その資金の管理権(印鑑の管理や入出金の決定権)が実質的に親にあるとみなされれば、それは贈与ではなく「親の財産」です。
そのため、せっかく節税のつもりで移転させたつもりが、相続発生時に全て親の遺産としてカウントされ、多額の相続税がかかってしまうケースが後を絶ちません。
②親族間での公平性を巡り「争族」へ発展するケース
手渡しで記録を残さないと、親族間での遺産争いの火種にもなります。特定の子どもだけが現金を受け取っていたことが後から発覚した場合、他の兄弟から「不公平だ」と不満が出たり、遺留分(法定相続人が最低限もらえる取り分)の計算に含めるべきだと主張されたりすることがあります。
このとき、明確な契約書や振込記録がないと、受け取った側も「それは贈与ではなく一時的な生活費の支援だった」などの反論ができないため、泥沼の争いに発展しかねません。
現金で贈与するならどうすべき?証拠の残し方と申告のポイント
手渡しした現金が「バレる・バレない」を心配して不安になるよりも、正々堂々と「贈与が成立した証拠」を積み上げておけば、何かあっても心配する必要はありません。そこで最後に、税務署に否認されない生前贈与のやり方について解説します。

「銀行振込」と「贈与契約書」をセットで運用する
最も推奨されるのは、手渡しではなく「銀行振込」による贈与です。通帳に記録を残すとともに、都度「贈与契約書」を作成しておけば、いつ・誰が・誰に・いくら渡したのかが明確になります。契約書には、贈与者と受贈者双方が署名・捺印し、受贈者が「自分の口座で管理している」という状態を作ることで、名義預金の疑いを晴らすことができます。
贈与税の申告をすべきケース
贈与税には、年間で110万円までの基礎控除が設けられています。したがって、その金額を超える贈与をした場合は、必ず期限内に受贈者の住所地を管轄する税務署へ申告しなければなりません。申告書を作成する際は、贈与契約書の内容と振込記録(通帳の写しなど)を照合し、事実関係に齟齬がないよう正確に記載しておきましょう。そうすれば、税務調査でのリスクを抑えることができます。
もし「過去の手渡し分をどう扱うべきか」「特例の適用要件に合致するか」など判断に迷う場合は、専門家である税理士に相談しておくと良いでしょう。そうすれば、状況に応じた最適なアドバイスが受けられます。
まとめ
生前贈与の現金手渡しは、適切に行えば将来の相続税を大幅に下げる効果があります。ただし、その恩恵を確実に受けるためには、単なる手渡しではなく、法的に有効な「贈与の実態」を証明できなければなりません。したがって、形式的な手続きで済ませるのではなく、銀行振込や契約書の作成を通じて客観的な証拠を残すことが不可欠です。
また、相続税対策は目先の税金だけでなく、二次相続まで見据えたものでなければなりません。一次相続の負担軽減だけを考えた安易な手渡しは、後に「名義預金」とみなされて相続税額が増えるだけでなく、親族内での遺産争いを招きかねません。こうした事態を防ぐためには、贈与を実行する前に税理士などの専門家に相談し、要件の確認や二次相続まで視野に入れたシミュレーションをしてもらうことをお勧めします。