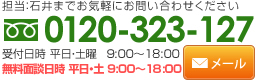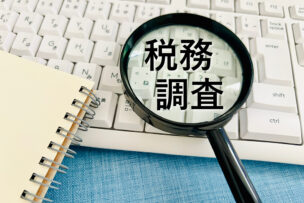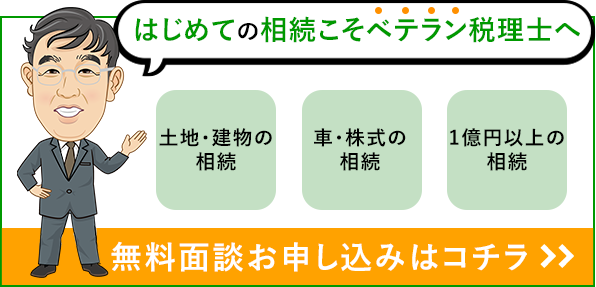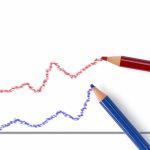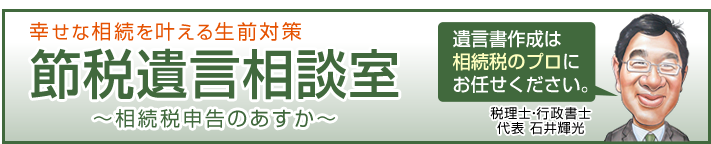souzoku-station
souzoku-station
相続税の税務調査は、特定の家庭が重点的に選ばれる傾向があります。特に2015年の税制改正で基礎控除額が引き下げられたことで、かつては相続税の申告が不要だった一般家庭も課税対象となり、調査対象が拡大しました。
では、どのような家庭が税務調査の対象になりやすいのでしょうか。本記事では、相続税の税務調査の基本や選ばれやすい家庭の特徴、そしてリスクを減らすための対策について解説します。
相続税の税務調査とは
相続税の税務調査は、特定の基準に基づいて実施されます。本章では、まずその仕組みや調査の流れについて解説します。
税務調査の対象となる割合
相続税の税務調査は、すべての申告に対して行われるわけではありません。国税庁の統計によると、申告された相続案件のうち、 税務調査が行われる割合は約10%前後とされています。
ただし、財産額が大きいケースや、申告内容に疑義がある場合は、調査の確率が上昇します。特に、財産評価の見直しや申告漏れの可能性があると判断されると、重点的に調査が実施される傾向にあります。
調査の流れとポイント
相続税の税務調査は、主に「書面調査」と「実地調査」の2種類に分かれます。書面調査は、提出された申告書の内容を税務署が確認し、不備や疑問点がある場合に、追加の資料提出を求めるものです。

一方、実地調査は、税務署の職員が直接訪問し、相続財産の評価や申告内容の正当性を確認するものです。実地調査では、預貯金の流れや不動産の評価方法、過去の贈与などが重点的にチェックされます。

一般家庭でも調査されるケース
2015年の税制改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、課税対象となる家庭が増えました。その結果、以前は相続税の申告が不要だった一般家庭でも、申告の必要が生じるケースが増加しています。
特に、相続財産のうち不動産の割合が高い家庭や、預貯金の動きが不透明な場合、税務調査の対象となる可能性が高くなります。また、申告内容に計算ミスや不明確な点があると、税務署から詳細な説明を求められることがあります。
無申告の相続に対する税務調査
相続税の申告義務があるにもかかわらず、無申告の場合、税務署が調査を行う可能性が非常に高くなります。特に、相続財産が一定額を超えている場合、銀行口座の動きや不動産の登記情報などから税務署が把握し、調査対象となると考えておいた方が良いでしょう。
また、遺産分割が行われた際に預貯金の大きな移動があると、税務署が相続税の申告漏れを疑い、追加の調査を実施するケースもあります。無申告が発覚した場合、延滞税や加算税が課されるため、早めの対応が重要です。
税務調査に選ばれやすい家庭の特徴とは?
税務署は、特定の基準に基づいて調査対象を選定しています。そこで、どのような家庭が調査の対象になりやすいのか、具体的な特徴について解説します。
相続財産の規模と構成
相続財産の総額が大きい家庭は、税務署が重点的に調査する傾向があります。特に、金融資産が2億円以上のケースや、不動産や非上場株式の割合が高い場合、適正な評価が行われているか慎重に確認されます。
また、相続財産が多岐にわたると、申告漏れのリスクが高まるため、税務調査の対象となる可能性が上がると考えられます。

申告内容の不備や疑問点
相続税の申告書に記載ミスや計算ミスがあると、税務調査の対象になりやすくなります。特に、税理士を介さずに自己申告した場合、誤りが発生しやすくなるため、税務署が疑問を持つことが多いです。
また、財産の移動履歴と申告内容が一致しない場合も、調査が実施される可能性が高くなります。
名義預金の存在が疑われる場合
家族名義の預金が多い場合、税務署は名義預金として相続税の課税対象と判断することがあります。特に、専業主婦や未成年の家族の口座に多額の預金があると、実質的には被相続人の資産だったと見なされやすいです。
また、過去の資金の流れが不透明な場合、詳細な説明を求められることもあります。
生前贈与が多い場合
生前贈与が頻繁に行われていると、税務署は相続税逃れの可能性を疑います。特に、2024年1月1日以降の贈与からは、死亡前の贈与が相続財産に含まれる期間が3年であったものが、7年に延長されることになりました。したがって、生前贈与が多い場合は、該当する金額については、必ず相続財産に含めなければなりません。
また、定期的に同じ金額を贈与するようなケースでは、贈与税の非課税枠を悪用したと判断される可能性があるため、注意が必要です。
海外資産を保有している場合
海外の銀行口座や不動産を相続した場合、税務署が申告漏れを疑う可能性があります。近年、日本の税務当局と海外の税務当局との間で情報共有を行う制度が強化されているため、必ず適正に申告を行わなければなりません。海外資産の申告を怠ると、追加課税や罰則が科されるリスクがあるため、慎重に対応することが重要です。
税務調査のリスクを減らすための対策
税務調査を避けるためには、適正な申告と事前の対策が重要です。ここでは、リスクを減らすための具体的な方法について解説します。
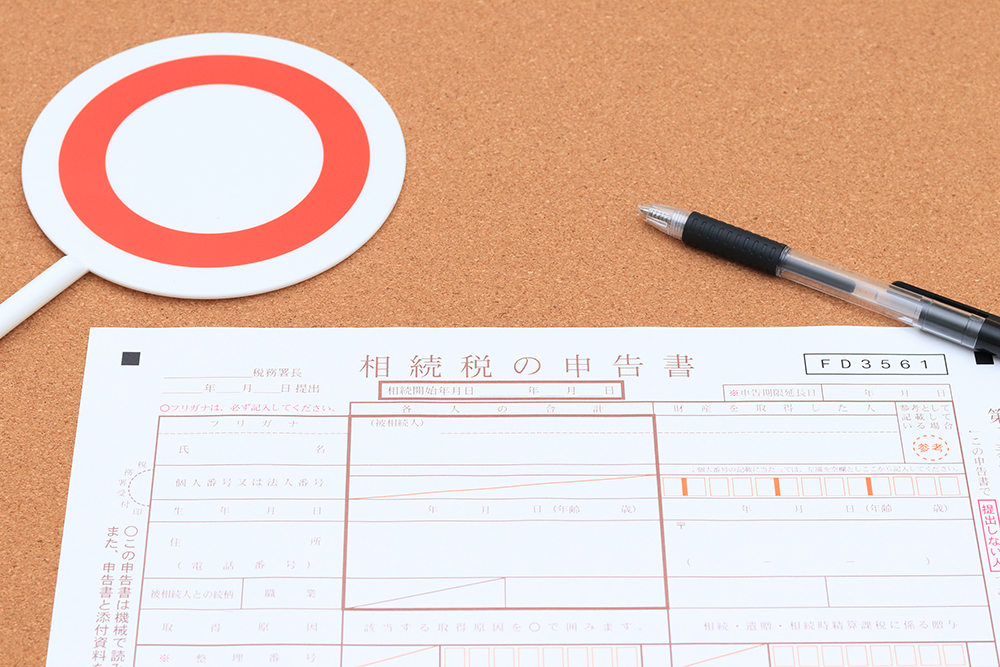
事前にできる相続税対策
相続財産の適正な管理は、税務調査のリスクを低減するための重要な鍵です。特に、不動産や金融資産の評価を早めに確認し、税務署から指摘される可能性のあるポイントを把握しておくことが大切です。
また、相続税の計算に影響を与える生前贈与についても、適切に記録を残し、何かあった場合税務署に説明できるように準備しておくことが大切となります。
申告書作成時の注意点
申告書の記載ミスや提出資料の不足は、税務調査の原因になります。財産評価の誤りを防ぐため、不動産の相続税評価に必要な資料や、預貯金の取引履歴などの整理を徹底しましょう。
また、名義預金や未申告の資産がないか、事前にチェックすることも必要です。税務署は申告書の不備に敏感なため、記載内容を丁寧に確認しておかなければなりません。
専門家に相談する
税理士は税の専門知識があるだけでなく、専門家として相続税の申告を何度も行っているため、「どこで間違えるのか」や「どうしたら間違えやすくなるのか」をよく知っています。したがって、相続税の申告を税理士に依頼すれば、相続税の申告ミスを防ぎ、税務調査のリスクを軽減できます。特に、相続財産が多岐にわたる場合や、海外資産を含む場合は、専門家の助言は不可欠と言えるでしょう。
また、税理士は、税務署の調査傾向を十分に理解しているため、適切な申告をサポートするだけでなく、万が一の場合には、調査の立会や税務署への対応もスムーズに進めることができます。
まとめ
本記事で述べたように、相続税の税務調査は、特定の条件に該当する家庭が対象になりやすい傾向にあります。そのため、こうした条件に当てはまる場合は、相続財産を正確に把握し、適切に申告を行わなければなりません。
2015年の税制改正により、多くの一般家庭も相続税の課税対象となったことから、税務調査のリスクが高まっています。こうしたリスクを避けるためには、相続税の税務申告を正しく行い、適正な相続税額を納税しなければなりません。
ただし、相続税の申告や税務調査に不安な方やアドバイスが欲しい方は、税の専門家である税理士に依頼すると良いでしょう。そうすれば、申告書の作成や税務調査についても、心配する必要がなくなります。