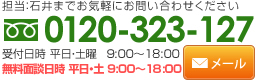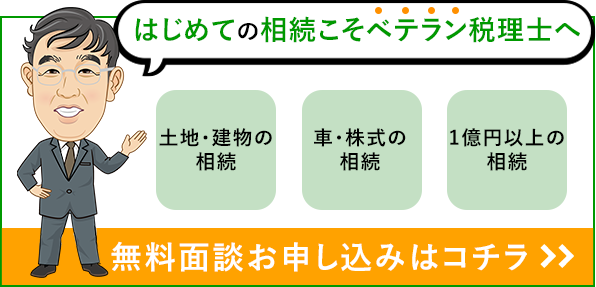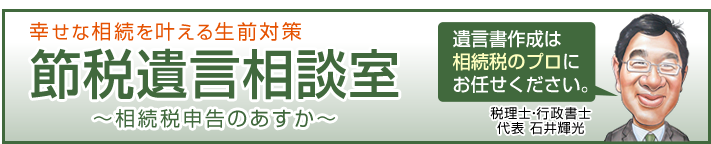souzoku-station
souzoku-station
相続税の計算で欠かせないのが「相続税評価額」です。なかでも土地の評価は複雑なため、多くの人が、どのように算定すべきか頭を悩ませるのではないでしょうか?
土地の評価には「路線価」や「固定資産税評価額」がありますが、選択を間違えると、正しい税額は算出できません。そこで本記事では、路線価を用いた評価の方法や固定資産税評価額との違いなどを整理したうえで、注意すべき点について解説します。
相続税評価額を決める「路線価」とは
はじめに、路線価とはどのような評価方法なのかを整理しておきましょう。

土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」
土地の相続税評価額を算出する際には、「路線価方式」か「倍率方式」のどちらかを用います。都市部や住宅地など多くの地域では、国税庁が公表する路線価を基準に評価する「路線価方式」が用いられます。
これに対し、郊外や山間部のように路線価が設定されていない地域では、「倍率方式」を使います。どちらの方式を用いるのかはあらかじめ定められているため、土地を評価する際には、国税庁のホームページなどで確認しておくことが重要です。
路線価の基本的な考え方
路線価とは、道路に面した標準的な宅地1平方メートルあたりの価格を示したものです。路線価は、毎年国税庁によって公表されており、相続税や贈与税を計算する際の重要な基準となります。
ちなみに、路線価は一般に公示価格のおおむね80%程度に設定されており、実際の取引価格より低めになる傾向にあります。相続税評価額を求める際には、多くの場合この路線価を出発点として、最終的な土地の評価額を算出することになります。
路線価図の見方と公表時期
路線価は、毎年7月ごろに国税庁から公開されます。地図上には道路ごとに1㎡あたりの金額が千円単位で示されており、例えば「200C」と記載されていれば、その道路に面する宅地1㎡の評価額は200×千円=20万円となります。
また、路線価図上のアルファベット(上述の200Cの場合は「C」)は「借地権割合」を示しており、その土地を借りている人が、評価額のうちどの程度を権利として扱えるかを示しています。
相続税評価額の計算方法と土地・建物の評価
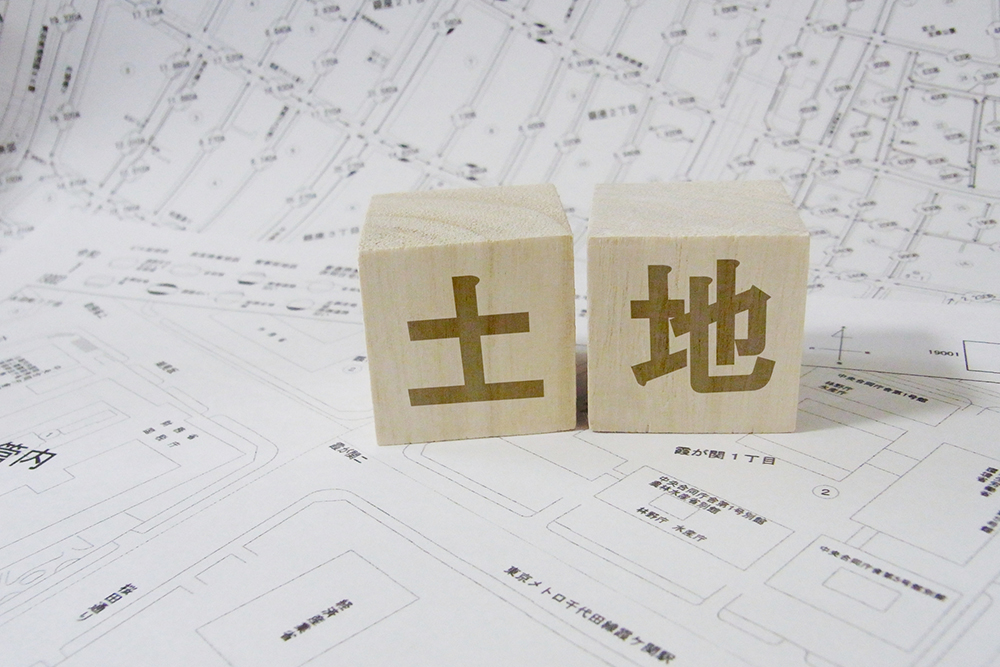
相続税評価額の計算方法は、土地と建物では異なります。ここでは、それぞれにどのような手順で評価額を計算していくのかを紹介します。
土地評価額の計算手順
土地の相続税評価額は、基本的に路線価に土地の面積を掛けて算出します。例えば、路線価が20万円で敷地面積が100㎡であれば、20万円×100㎡=2,000万円が相続税評価額です。
ただし、実際にはこのような単純な計算にはとどまらず、土地の形状や利用状況に応じて補正を加えなければなりません。「間口が狭い」「奥行が深い」「不整形、角地である」などの場合には、定められた補正率を用いて調整を行い、最終的な評価額を算出します。
それだけでなく、上述の借地権も、評価に影響します。したがって、土地評価額を正しく算定するためには、路線価の確認に加え、具体的な土地の状況を丁寧に反映させなければなりません。
建物の評価額の考え方
建物の相続税評価額については、土地とは異なり、路線価でなく固定資産税評価額を用います。固定資産税評価額とは、市町村が3年ごとに見直しを行い、新築時の建築費や築年数に伴う減価などを考慮して算出したものです。
建物の相続税評価額は、この固定資産税評価額をそのまま用います。したがって、土地は路線価方式または倍率方式で評価し、建物は固定資産税評価額で評価する、ということになります。
固定資産税評価額との違いとその影響
路線価と固定資産税評価額は混同されやすいですが、用途や算定基準が異なるため、注意しなければなりません。

路線価と固定資産税評価額の役割の違い
路線価は相続税や贈与税の計算に用いられる基準であるのに対し、固定資産税評価額は毎年課される固定資産税や不動産取得税、登録免許税などの算定に使われます。いずれも土地や建物の価値を示しますが、その目的は同じではありません。
また、固定資産税評価額は公示価格のおよそ70%であるのに対し、路線価はおおむね80%程度に設定されることが多いため、同じ土地であっても両者の評価額が一致することはありません。そのため、「どちらの評価額がどの税金に用いられるか」を正しく理解しておかないと、相続税の申告時に誤った基準を使い、税額を誤算する危険があります。
評価額を間違えた場合の税額への影響
路線価と固定資産税評価額の差は、相続税額に直結します。例えばある土地について、固定資産税評価額が1,400万円、路線価に基づく評価額が1,600万円だったとします。ではもし、路線価と固定資産税評価額を取り間違えてしまったらどうなるでしょうか?
仮に、相続税率が10%なら、(1,600万円-1,400万円)× 10% = 20万円 だけ税額が少なくなってしまいます。これが税率20%なら、(1,600万円-1,400万円)× 20% = 40万円です。
このように、基準を取り違えるだけで数十万円単位の差が生じ、加算税などのリスクを負うことになります。そうならないためには、必ず路線価を基準に計算しましょう。
小規模宅地等の特例等、注意すべきポイント

相続税評価額を大幅に減額できる制度には、小規模宅地等の特例があります。最後に、この特例の概要と注意すべき点について解説します。
小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に住んでいた宅地や事業用の宅地などについて、相続税評価額を大幅に減額できる制度のことです。例えば、自宅の宅地を相続する場合は、最大330平方メートルまで評価額を80%減額できます。
また、事業用や賃貸用宅地にもそれぞれ減額割合や限度面積が設定されているため、条件を満たせば相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。この特例は、多くの相続で活用されている制度であり、納税資金の確保や円滑な財産承継に大きな効果を発揮しています。
特例を利用する際の注意点
小規模宅地等の特例は、納税者にとって非常にありがたい制度ですが、適用するには細かい条件があるため注意が必要です。例えば、自宅の宅地で特例を受けるためには、相続人が申告期限まで引き続き居住していなければなりません。
また、特例を適用するためには期限内に相続税の申告を行わなければならず、1日でも期限を過ぎるとせっかくの減額が受けられません。さらに、小規模宅地等の特例を適用した宅地を相続直後に売却すると、特例が取り消されてしまう可能性があります。
このように、特例を受けるためにはさまざまな要件を満たさなければならないため、心配な方は、事前に税理士などの専門家に相談しておくと良いでしょう。
まとめ
相続税評価額は、土地では路線価、建物では固定資産税評価額を用いて算定されます。両者は目的や基準が異なるため、混同しないように注意する必要があります。小規模宅地等の特例を活用すれば評価額を大幅に減額できますが、条件を満たさなければ適用が認められないこともあります。そのため、後々の負担が大きくならないように、早めに税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。