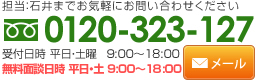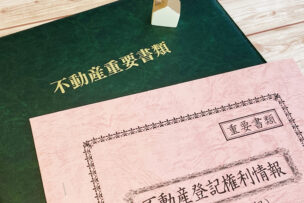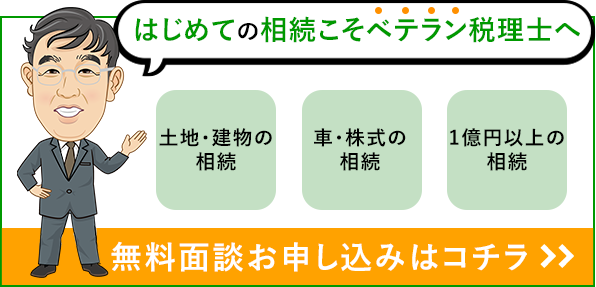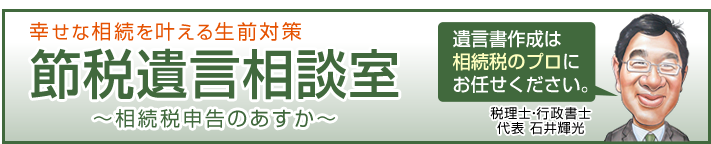souzoku-station
souzoku-station
不動産を相続する際には、「相続登記」と呼ばれる手続きが必要になります。これまでは登記をしなくても罰則はありませんでしたが、法律が改正され、登記が義務化されました。
その結果、放置した場合には最大10万円の過料が科されることになるため、早めに対応をしなければなりません。そこで本記事では、新制度の内容と登記が必要なケース、今確認しておくべきポイントなどについてわかりやすく解説します。
そもそも相続登記とは?
不動産を引き継ぐ際に必要になるのが、「相続登記」と呼ばれる手続きです。名前は聞いたことがあっても、その意味や必要性については、まだまだ十分に知られていないのではないでしょうか。
そこでまず、相続登記がどういう仕組みなのか、そして手続きを怠るとどうなるのかについて解説します。
相続登記とは何か、なぜ必要なのか
不動産を相続し、法的に「自分のもの」と認められるためには、名義の変更手続きが必要です。この手続きを「相続登記」といいます。登記とは、法務局に対して「この不動産の所有者は誰か」という情報を登録する制度であり、これを行わないと、たとえ遺産として受け継いだとしても、正式な所有者としては扱われません。
また、相続登記を完了していないと、不動産を売ったり担保に入れたりすることもできません。したがって、相続した不動産の権利を守るためにも、相続登記は非常に重要なステップとなります。
登記が行われていない場合の問題点
相続登記をせずに不動産をそのまま放置しておくと、思わぬトラブルが発生することがあります。例えば、他の相続人に勝手に売却されてしまったり、次の世代へと相続が繰り返された結果、相続人が増えてしまい、名義を整理するのが非常に困難になってしまったりすることなどです。
それ以外にも、登記されていない不動産が空き家として放置された結果、地域の防災や治安、景観の問題にもつながる可能性があります。こうしたことを防ぐためにも、相続登記は早めに済ませておくことが大切です。

相続登記が義務化された理由
相続登記は相続時に必要な手続きですが、詳しい内容を知らないまま放置しているケースも多く見られます。そこでこの章では、相続登記の役割や、手続きをしないことで起こる問題について解説していきます。
所有者不明土地が社会に与える影響
相続登記をせずに放置された土地や建物の中には、所有者が不明なまま何十年も放置されているものがあります。こうした不動産は「所有者不明土地」と呼ばれ、公共事業が進められなかったり、空き家のまま地域の治安や景観に悪影響を与えたりと、さまざまな社会問題につながってきました。
政府の調査によれば、日本全国で所有者がわからない土地の合計面積は、すでに九州全体の面積を上回っているともいわれています。これは地域にとっても国家全体にとっても、非常に大きな課題となっています。
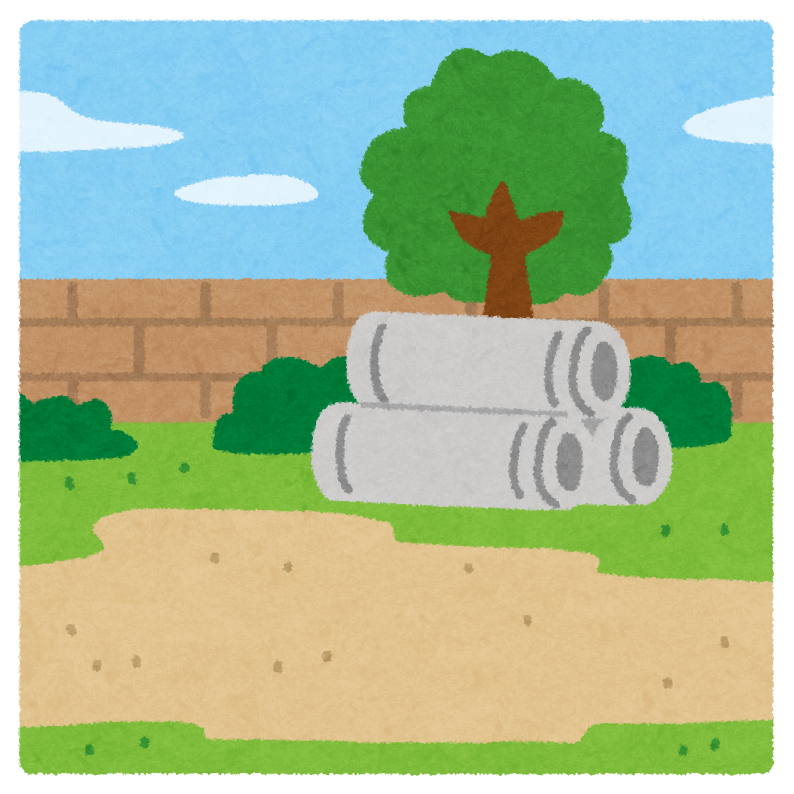
制度改正によって何が変わるのか
こうした状況を受けて、政府は相続後の不動産について、登記を義務化する方針を打ち出しました。これにより、土地や建物のように登記が必要となる財産を相続した場合は、一定の期間内に名義変更の手続きを行うことが求められるようになりました。
この制度改正の目的は、不動産の所有者情報を把握しやすくし、地域の再開発や公共インフラ整備を円滑に進めることです。また、相続を「済んだつもり」のまま放置することを防ぎ、次の世代へと問題が引き継がれないようにする狙いもあります。
新制度の概要と注意点
2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合には、登記の手続きを行うことが法律で義務づけられました。そのため、どのような相続が対象になるのか、いつまでに登記すればよいのか、罰則があるのかなど、何がどう変わったのかを正しく理解しておくことが重要です。
そこで本章では、義務化された新制度の内容と押さえておくべき注意点を、わかりやすく整理していきます。
義務化の対象となる相続と登記の範囲
制度の転換点となったのは、2024年4月1日です。この日以降に発生した相続で不動産を取得した場合には、名義変更する登記を行うことが法律上の義務となりました。正当な理由なく手続きを怠った場合は、罰則として最大10万円の過料が科されることとなります。

登記の義務は、法定相続に限らず、遺言による相続や遺産分割協議を経て取得した場合も対象になります。つまり、「どういう経緯で相続したか」にかかわらず、不動産を取得した人すべてに義務が生じるわけです。
また、2024年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、登記が済んでいなければ義務の対象となります。ただし、これらの過去分については2027年3月31日までという3年間の猶予期間が設けられているため、それまでに登記を完了させることで過料を回避することができます。
手続きの期限と「過去分」の扱い
相続登記の手続きの期限は、相続があったことを知ってから3年以内です。これは、2024年4月1日以降に発生する相続だけでなく、それ以前の相続にも猶予期間付きで適用されます。
たとえば、10年前に親を亡くしたものの手続きをしていなかった場合、2024年4月から数えて3年以内、つまり2027年3月末までに登記を済ませなければなりません。したがって、過去に相続した方も、登記が済んでいない場合は、期限内に済むようにできるだけ早く手続きを進めておく必要があります。
費用の目安と過料のリスク
相続登記を行う際には、法務局で登録免許税を支払わなければなりません。金額は不動産の評価額の0.4%が目安となっており、たとえば評価額が1,000万円であれば、約4万円の登録免許税が必要となります。
ただし、一定の条件を満たせば軽減措置を受けられるケースもあるため、事前に法務局などで確認しておくと良いでしょう。
また、正当な理由なく登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は罰金とは異なり前科にはなりませんが、不要な出費ではあるため、期限内に手続きを終えるように早めの対応を心がけましょう。
実務対応のステップ
制度の内容が理解できても、「具体的に何から始めればいいのか」が曖昧なままでは、対応が後回しになってしまいます。そこで最後に、相続登記の実務において必要な確認事項や準備すべき書類、専門家に相談すべきタイミングなどについて解説します。
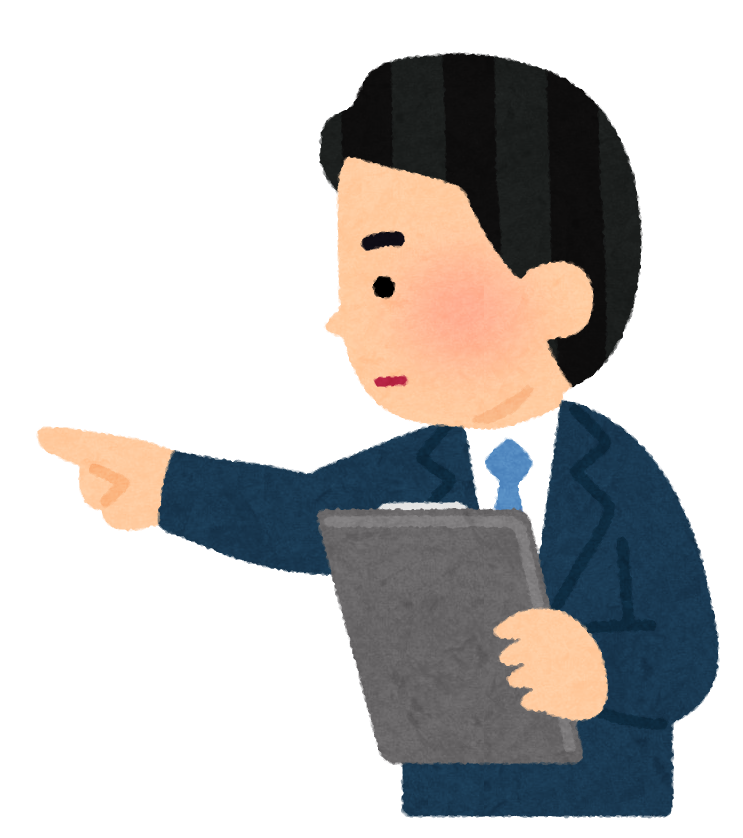
まず確認しておくべきこと
相続登記を進めるにあたって、最初にすべきことは「自分が相続人かどうか」「どの不動産が対象か」を明らかにすることです。そのため、被相続人(亡くなった方)の戸籍をさかのぼって確認し、相続関係説明図などを作成しておくと良いでしょう。
あわせて、相続対象となる不動産の情報も正確に把握しなければなりません。不動産の所在地や地番、評価額は、市区町村が発行する固定資産税納税通知書や名寄帳、または法務局の登記事項証明書などで確認します。
書類の準備と専門家への相談
相続登記を行うには、必要な書類を漏れることなく揃えなければなりません。主な書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票、該当する不動産の固定資産評価証明書、登記申請書などです。
また、遺言がある場合や遺産分割協議が成立している場合には、それらの写しや協議書も必要になります。
こうした書類の収集や作成には専門的な知識が必要となる部分も多いため、司法書士や税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。とくに、相続人が遠方に住んでいたり、不動産が複数あったりするような場合、登記手続きが煩雑になりやすいため、早目に専門家に依頼しておくと良いでしょう。

まとめ
相続登記の義務化により、不動産を受け継いだ際には、登記の手続きをきちんと済ませておくことが法律上のルールとなりました。先延ばしにしがちな相続登記手続きも、明確な期限が設けられた今だからこそ、早めに対応しておくことが大切です。
必要な情報を整理し、書類を準備しておけば、初めての方でも登記手続きを行うことは可能です。とはいえ、「手続きに不安がある」「状況が複雑かもしれない」と感じたら、専門家の手を借りると良いでしょう。家族の将来にわずらわしさを残さないためにも、相続登記を確実に済ませるようにしましょう。