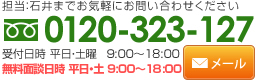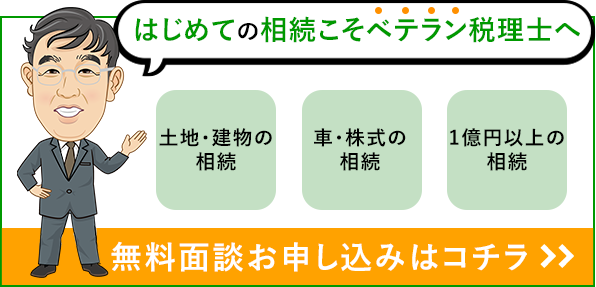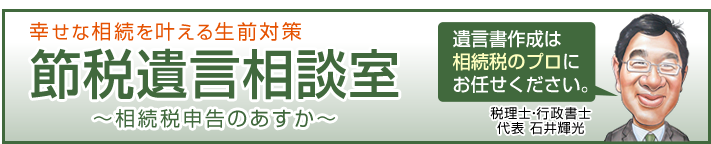souzoku-station
souzoku-station
父が亡くなり、母が認知症という状況に直面すると、多くの人はどう手続きを進めればよいのか、不安を抱く方も多いのではないでしょうか?遺産分割協議や財産管理、相続税の申告など避けられない課題が山積みとなり、認知症の影響で手続きが進まないケースも少なくありません。
そこで本記事では、認知症が絡む相続で生じやすい問題点と、それに対応するための制度や方法を紹介します。
父が亡くなったときに必要な相続手続きの基本

はじめに、相続の基本的な手続きについて確認しておきましょう。
相続人と法定相続分の確認
父が亡くなった際、最初に行うべきことは、誰が相続人になるのかの確認です。民法では、配偶者である母は常に相続人となり、子どもがいればその子どもも相続人となるように定めています。子がいない場合は、配偶者に加えて直系尊属(父母や祖父母など)や兄弟姉妹が相続人となります。これが、相続人を特定するための基本ルールです。
次に、相続人の持分についてです。法定相続人の持ち分は、「法定相続分」としてその割合が法律で定められています。例えば、配偶者と子ども二人が相続する場合、その持ち分は、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつです。
遺産分割協議と相続税申告の流れ
相続人が確定したら、遺産の範囲を調べ、遺産分割協議を行います。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印をして全員で保管します。遺産分割協議書は、不動産登記や銀行手続き、相続税の申告などに必要となる非常に重要な書類です。したがって、作成は慎重に行わなければなりません。
また、相続税の課税対象となる場合には、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。申告期限を過ぎると延滞税や加算税が課されるため、早めに準備を進めておいた方が良いでしょう。相続財産の評価や税額計算には専門知識が求められることから、相続人だけで進めるのが困難な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
母が認知症のときに生じる相続の問題点
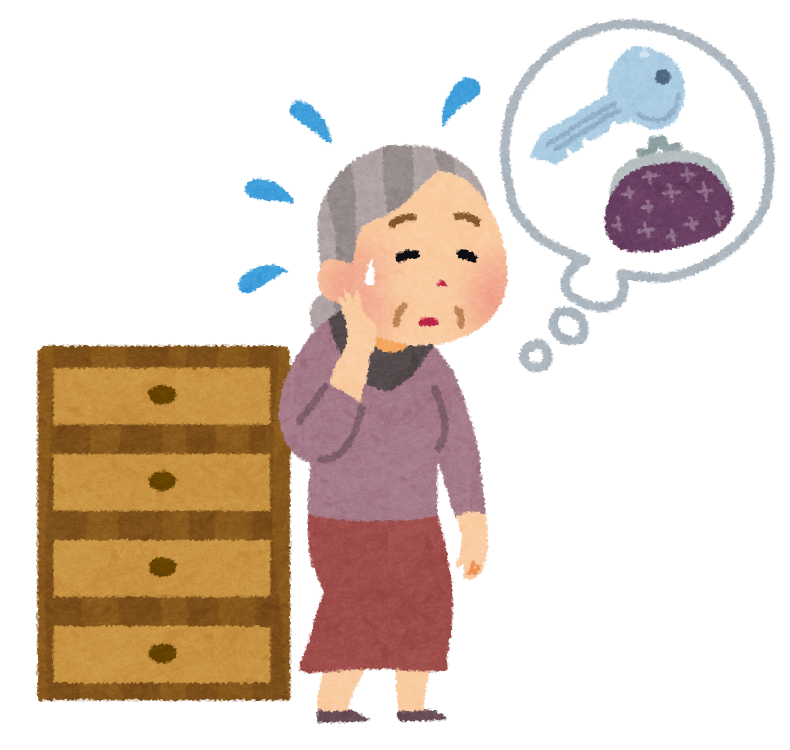
次に、相続人である母が認知症である場合、どのような問題が生じ得るのかについて考えてみましょう。
遺産分割協議に母が参加できない問題
相続手続きの中心となる遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意することが原則です。ですが、母が認知症で判断能力を失っていれば、本人が協議の内容を理解し、意思表示をすることができません。
仮にこのような状態で署名や押印をしても、法的には無効とみなされるため、協議そのものが成立しません。そのため、遺産の分け方が決められず、相続手続き全体が滞ることになります。
預貯金や不動産の管理・処分ができないリスク
母が認知症で意思能力を欠いている場合、日常生活に必要な資金を銀行口座から引き出すことや、不動産を処分して相続税の納税資金を準備することが困難になります。金融機関は本人の意思確認を厳格に行うため、家族の判断だけでは、基本的に被相続人の口座は解除されません。
したがって、相続税の申告期限までに、納税資金が用意できないリスクが生じます。また、不動産の名義変更や売却も同様に本人の同意が求められるため、手続きを進めるに際し、大きな障害となることも考えておかなければなりません。
母が認知症のとき家族信託は利用できる?その限界と注意点

被相続人の認知症対策として、近年では「家族信託」の活用が増えています。そこで、家族信託の基本的な仕組みを紹介するとともに、その限界や注意点について解説します。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託とは、本人が保有する財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用を任せる仕組みのことです。不動産や有価証券などを対象とし、受託者となる家族が、契約に基づき管理を行います。
たとえば、母が元気なうちに「生活費の支払いを子どもが代行する」といった内容を契約で定めておけば、母に代わって財産を使いながら生活を支えることができます。そのため、認知症になる前の準備として、近年では多くの方に利用されています。
認知症発症後に利用できない理由と事前準備の重要性
家族信託は便利な制度ですが、認知症発症後には新たに契約を結ぶことができません。契約の有効性を担保するには本人の意思確認が不可欠ですが、その判断能力が欠けている状態では、法的に成立しないためです。
したがって、家族信託を利用するためには、母が元気なうちから準備を進めておかなければなりません。そうすれば、万が一認知症を発症したとしても、相続の手続きで生じるトラブルを避けることができるでしょう。
母が認知症の場合に活用できる成年後見人制度

家族信託は、(推定)相続人が高齢な場合の認知症対策には非常に有効ですが、発症後に新たに契約を結ぶことはできません。したがってこのようなケースでは、成年後見制度の活用が現実的な解決策となります。
そこで本章では、成年後見制度とはどのような制度で、その手続きや流れ・費用の目安はどれくらいなのかについて解説します。
成年後見人の役割と権限
成年後見人制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人に代わり、財産管理や法律行為を行う制度のことです。家庭裁判所によって選任された成年後見人は、本人に代わって預貯金の引き出しや不動産の売却、遺産分割協議などを行います。
たとえば、母が相続人でありながら協議に参加できない場合、この制度を利用することで、代理人が母に代わって手続きを進めることができます。それだけでなく、成年後見人には定期的な報告義務が課されているため、不正利用を防ぐための監督の仕組みも整えられています。
申立てから選任までの流れと費用の目安
成年後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。申立てを行えるのは、配偶者や子ども、四親等内の親族などに限られており、医師の診断書や戸籍関係書類を揃えて提出します。
家庭裁判所の審理を経て、後見人が選任されるまでには通常1〜2ヶ月程度かかりますが、ケースによってはさらに時間を要することも珍しくありません。また、費用面については、申立て自体に数千円から1万円程度が必要となります。
さらに、「誰が後見人になるか」や「管理する財産の規模」、「業務の複雑さ」などに応じ、選任後に成年後見人に対して報酬が必要となる場合もあります。このように、成年後見人制度には経済的な負担はありますが、相続を円滑に進めるためには欠かせない制度です。
まとめ
父が亡くなり、母が認知症という状況では、相続手続きは通常よりも格段に複雑化します。「遺産分割協議に参加できない」「財産管理が滞る」「相続税の納税資金を準備できない」など、深刻な問題も生じかねません。
こうしたケースに対する予防策として、家族信託は非常に有効ですが、認知症の発症後には使えません。したがって、その場合は、成年後見制度の利用を検討しなければなりません。どちらの制度を活用すべきかには専門知識が必要となるため、心配な方は早い段階で税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。