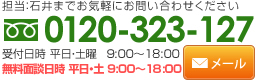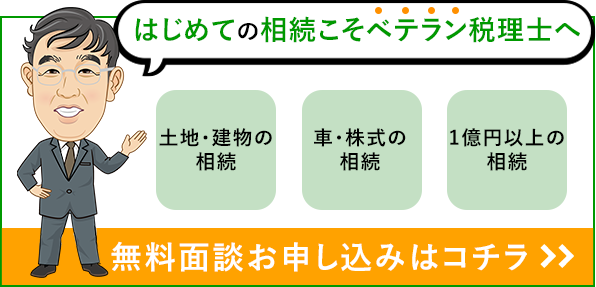souzoku-station
souzoku-station
平成27年の税制改正により相続税が大幅に改正されました。これまで相続税は、一定以上の資産を持った人だけにしか関係のないものでした。ところがこの改正により、多くの人にとっても相続税は他人事では済まなくなってしまったのです。
しかし一方で相続税にはさまざまな特例があり、実際に条件さえ合えば非常に多くの控除を受けることができます。
それにも関わらず、こういった特例や控除に関する知識がないばかりに、本来支払うべき相続税を超える多額の納税をしてしまうケースが多発しています。
そこで本日は、そういったケースを防ぐために相続税に使えるさまざまな特例について解説していきます。誰でも使える相続税に関する特例・一部の人しか使えない特例など一概に相続税の特例と言ってもいくつか種類があります。
特例の種類から注意点まで詳しくみていきましょう。
誰でも使える相続税の特例
まずは誰でも使える相続税の特例についての解説です。
相続税の基礎控除について
相続税は全ての人に支払い義務があるわけではありません。基礎控除額を超えた財産を相続した場合に、相続人が相続税を負担することになっています。
相続した額が基礎控除額に満たない場合、相続税を支払う必要はありません。基礎控除額の計算方法についてみていきましょう。
基礎控除の金額と計算方法
基礎控除の金額は、誰でも同じではありません。基礎控除の金額は、法定相続人の数によって決まります。なお基礎控除の金額の以下の計算方法によって算出します。
基礎控除の金額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば法定相続人が母、自分、妹の3人の場合、基礎控除の金額は
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
法定相続人の数に含まれるもの
法定相続人には相続を放棄した人も含まれます。また実子がいる場合は1名、いない場合は2名までの養子も相続税の法定相続人に含まれます。
さらに被相続人よりも相続人が早く亡くなっている場合、相続人の子供が亡くなった相続人に代わって相続をします(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます)が、仮に子供が2人いれば、2人とも法定相続人となります。
養子縁組や代襲相続が行われる場合は法定相続人の数が増え、基礎控除の金額もそれにともない増えるため、計算する時にはこれらに留意しなければなりません。
基礎控除について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

一部の人が使える特例
続いては一部の人のみが使える特例についてみていきましょう。
配偶者の税額軽減の特例
配偶者が相続する分に限り、法定相続分もしくは1億6千万円までのうち、金額の高い方を相続する財産から控除してもらえます。この特例を「配偶者の税額軽減の特例」といいます。
この「配偶者の税額軽減の特例」は、被相続人を亡くしてしまった配偶者に対する生前の寄与と老後の生活への配慮から設けられています。
例えば相続財産が10億円、相続人が母、自分、妹の3名で法定相続分に応じて相続を行う場合、母親が相続する5億円については「配偶者の税額軽減の特例」によって相続税が非課税となり、自分と妹が相続する分にのみ相続税が課税されます。
このように、特例によって配偶者である母親は相続税が非課税となります。
未成年者の税額控除
相続人が未成年である場合、特例として10万円×(20-相続時の年齢)で計算された金額分が相続税額から控除されます。
例えば16歳で相続した場合、10万円×(20-16)=40万円が相続税額分から差し引かれます。
障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から以下で計算した金額が差し引かれます。
一般の障害者の場合:(85歳になるまでの年数)×10万円
特別障害者の場合:(85歳になるまでの年数)×20万円
例えば一般の障害者に該当する方で年齢が65歳の場合、
(85-65) ×10万円=200万円 が相続税額分から差し引かれます。
相次相続控除
10年以内に2度の相続があった場合「相次相続控除」の特例によって、一定の金額が税額控除されます。「10年以内に2度の相続」とは、例えば父が亡くなり、その10年以内に母が亡くなった場合をいいます。
この場合、1度目の相続で支払った相続税額が、その経過年数に応じて計算した分だけ2度目の相続で差し引かれます。
- 相次相続控除について詳しくはこちら:相次相続控除って?10年以内に2回相続が発生したら要チェック
贈与税控除
相続が発生する前3年の間に被相続人から相続人への生前贈与があった場合は、その生前贈与の額を相続税に加算しなければなりません。
ただし相続発生前3年内の間に贈与税を納税していた場合、「贈与税控除」の特例として贈与税額分を相続税から控除することができます。
- 贈与税が非課税となる場合について詳しくはこちら:贈与税が非課税となる全5パターン+α
外国税額控除
海外に財産があり、その財産に関して海外で相続税を支払った場合、支払った相続税を日本で支払う相続税から控除することができます。
この特例を「外国税額控除」といいます。
相続時精算課税制度贈与税額の控除
被相続人が生前に相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払っていた場合、特例として相続税額から相続時精算課税制度における贈与税額を控除することができます。
- 相続時精算課税制度について詳しくはこちら:相続時精算課税制度を利用すると良いケースと手続きの流れ

小規模宅地の特例
相続時の特例の中でも最も大切な特例と言っても過言ではないのが、「小規模宅地の特例」です。
被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について一定の要件を満たす場合、80%または50%まで評価額を減額してもらえる特例です。
土地の評価額が下がることで、相続税の減額につながります。小規模宅地の特例を受けるための条件についてみていきましょう。
特例を受けるための要件
小規模宅地の特例を受けるためにはいくつかの要件を満たさなくてはなりません。
特例を受けるための要件1:事業又は居住用の宅地であること
小規模宅地の特例を受けるためには、その土地が被相続人(もしくは被相続人と生計を一にしていた親族)の事業又は居住の用に供されていた宅地等である必要があります。
特例を受けるための要件2:建物又は構築物の敷地であること
小規模宅地の特例を受けるためには、1で該当する宅地等が、建物又は構築物の敷地でなければなりません。
特例を受けるための要件3:1・2を満たした上で以下の要件を満たすこと
1,2の要件を満たした上で、更にこの土地が以下の要件を満たさなければなりません。
- 被相続人が住んでいた土地の場合・・・被相続人の配偶者、同居親族等が相続すること
- 被相続人が事業をしていた土地の場合・・・被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、事業を申告期限まで継続すること。さらにその宅地等を申告期限まで保有すること
- 被相続人や被相続人の親族が経営していた法人に貸していた土地の場合・・・その法人に相当の対価で宅地等を賃貸し、その宅地を相続した親族が申告期限まで法人の役員であり、その宅地を申告期限まで保有すること
- 被相続人等が貸付事業をしていた宅地の場合・・・被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、それを申告期限まで継続し、その宅地を申告期限まで保有すること
これらの要件を全て満たした場合に限り、一定の面積まで土地の評価額を減額することができます。

相続税の特例を使う場合の注意点とポイント
続いては、これまでご紹介した特例を利用する場合の注意点とポイントについてみていきましょう。
基礎控除と特例の併用はできません
基礎控除とこれまでご紹介したそれ以外の特例を併用することはできません。
例えば基礎控除が6千万円である場合、配偶者控除の特例の1億6千万円と合わせて2億2千万円までの控除が行えるというわけではありません。
納税額が0円でも申告をする必要があります
基礎控除を使って相続税が非課税となった場合は、相続税に関して特に申告する必要はありません。ただし、特例を使って相続税が0円となった場合には、申告の必要があります。
例えば相続財産の総額が1億6千万円を下回る場合、被相続人の配偶者が全ての財産を相続し、配偶者の税額軽減の特例を利用すれば相続税額は0円となります。ただしこの場合は特例を利用しているため、相続税についての申告が必要です。
一方、相続財産の総額が5千万円で基礎控除を計算すると6千万円だった場合、相続税は非課税となります。この場合には申告の義務はありません。
特例を利用して相続税が0円となった場合で申告をしなかった場合、後日税務調査が行われると特例は使われなかったものとして納税しなければならなくなるので注意しましょう。
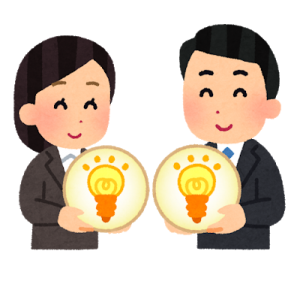
まとめ
今回は相続税の特例について詳しくみていきました。
特例を利用して相続税を減額する場合、必ず申告が必要なことを覚えておきましょう。
ただし、相続税の申告は一般的な税理士でも慣れていない事が多いです。正しく相続税について申告し、確実に特例を使って納税額を0円にするためには相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。