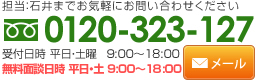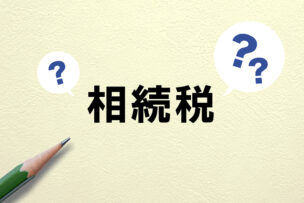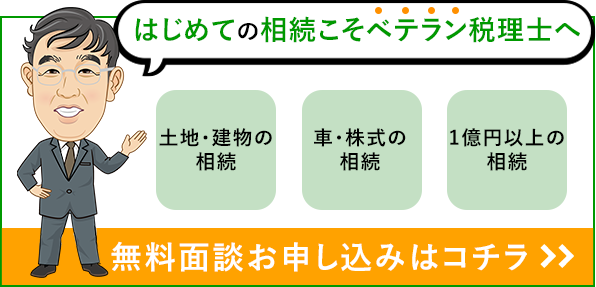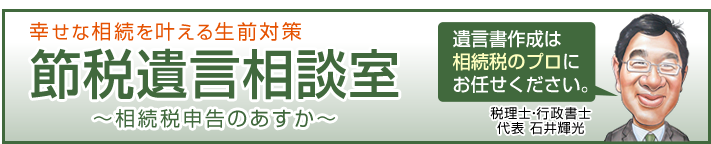souzoku-station
souzoku-station
あなたがもし、ある日突然、3億円もの財産を相続したらどうでしょう? 喜びよりも先に、もしかしたら『相続税はいったいいくらになるのだろう?』という疑問が頭をよぎるかもしれません。
本記事では、そんなあなたの疑問にズバリお答えします。3億円の相続税を徹底シミュレーションし、大切な資産を守るための賢い対策を具体的に解説します。
3億円の相続税シミュレーション
はじめに、相続財産が3億円の現金であると仮定した場合、相続人の構成によって相続税額がどのように変わるのかを試算してみましょう。その前にまず、相続税の計算手順のおさらいからです。

相続税の計算の基本的な手順
相続税は、大まかに分けると、以下の5つのプロセスを経て税額を算出します。
- 課税価格の合計額の算出・・・今回は3億円(現金)
- 基礎控除額の算出・・・「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
- 課税遺産総額の算出・・・「課税価格の合計額 − 基礎控除額」
- 法定相続分に応じて按分し、各人の相続税を個別に計算・・・税率は累進制(10%〜55%)で、控除額あり
- 配偶者の税額軽減を適用(課税価格1.6億円 or 法定相続分までは非課税)
では、実際に以下のケースごとに、それぞれの相続税額を算出してみましょう。なお、相続税額は、以下の速算表を用いて算出します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
|
1,000万円超から 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
|
3,000万円超から 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
|
5,000万円超から 1億円以下 |
30% | 700万円 |
|
1億円超から 2億円以下 |
40% | 1,700万円 |
|
2億円超から 3億円以下 |
45% | 2,700万円 |
|
3億円超から 6億円以下 |
50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(引用元:国税庁ホームページ「No.4155 相続税の税率」より)
①配偶者のみ(法定相続人1人)
法定相続人が配偶者のみの場合、3億円の相続税額は、以下のようになります。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×1人=3,600万円
- 課税遺産総額:3億−3,600万円=2億6,400万円
- 全額を配偶者が相続(法定相続分100%)
- しかし配偶者の税額軽減により「法定相続分」または「1.6億円」まで非課税 → 相続財産のすべてが法定相続分のため、この場合全額が非課税におさまる。
- 納税額:0円
②配偶者+子1人(法定相続人2人)
法定相続人が配偶者と子供1人の場合、3億円の相続税額は、以下のようになります。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×2=4,200万円
- 課税遺産総額:3億−4,200万円=2億5,800万円
- 法定相続分:配偶者1/2(1億2,900万円)、子1/2(1億2,900万円)
- 【相続税の計算】
配偶者 → 配偶者の税額軽減により全額非課税
子:1億2,900万円 × 40% − 1,700万円=3,460万円 - 納税額:3,460万円(子のみ)
③配偶者+子2人(法定相続人3人)
法定相続人が配偶者と子供2人の場合、3億円の相続税額は、以下のようになります。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 課税遺産総額:3億−4,800万円=2億5,200万円
- 【法定相続分】
・配偶者:1/2 → 1億2,600万円
・子2人:各1/4 → 6,300万円ずつ - 【相続税の計算】
配偶者 → 配偶者の税額軽減により全額非課税
子(各6,300万円)
・税率30%、控除額700万円
・6,300万円×30%−700万円=1,190万円/人 - 納税額:2,380万円(子2人で合計)
このように、3億円の現金を相続しても、相続人の内訳によってこのように納税額が大きく変わります。
3億円の遺産を無駄にしない節税対策
上述のように、相続税は、相続人の内訳によって、その税額が大きく変わります。それだけでなく、3億円の相続財産の内訳によっても、相続税額は大きく変わります。なぜなら、相続財産によっては、評価額を下げる特例などがあるためです。
そこで、こうした相続税の特徴を利用した節税方法のうち、代表的なものをいくつか紹介します。

生前贈与を活用する
贈与税には、年間110万円までの非課税枠があります。これを活用し、計画的に贈与を行うと、将来の相続財産を減らすことができます。
ただし、2024年1月1日からは、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されてしまうため、相続財産を減らすためには、できるだけ早くから対策をする必要があります。
不動産で相続税を抑える
不動産は、特例を適用することで、さらに評価額を下げることができます。たとえば、3億円の遺産のうち、1億円が自宅の土地(200㎡)だったとしましょう。
この土地に対して「小規模宅地等の特例」が適用できると、一定の要件のもとで評価額を80%減額できます。
自宅の土地の相続税評価額・・・1億円 × (1 – 0.8) = 2,000万円
つまり、相続税評価額が1億円の土地が、特例により2,000万円として評価されることになり、課税遺産総額を大きく減らす効果が期待できます。
賃貸不動産で相続税を抑える
たとえば、3億円の遺産のうち、1億5,000万円が賃貸アパートの土地(150㎡)だったとしましょう。この土地に対して「貸付事業用宅地の特例」を適用できると、一定の要件のもとで評価額を50%減額できます。
賃貸アパートの土地の相続税評価額・・・1億5,000万円 × (1 – 0.5) = 7,250万円
これにより、相続税評価額が1億5,000万円の土地が、特例により7,250万円として評価されることになります。さらに、賃貸割合に応じて借家権割合も評価額から控除されるため、より節税効果が高まります。
生命保険で相続税を抑える
相続人が受け取る死亡保険金には、以下の非課税枠が設けられています。
非課税限度額の計算・・・500万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人だった場合、生命保険の非課税限度額は、以下のようになります。
生命保険の非課税限度額・・・500万円 × 3人 = 1,500万円
したがって、もし、相続人が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円以下であれば、その保険金には相続税が課税されません。そのため、3億円の遺産の中に、生命保険金2,000万円が含まれていたとしても、非課税枠1,500万円を差し引いた500万円のみが相続税の課税対象となります。
生命保険は、非課税枠を活用できるだけでなく、納税資金を準備する手段としても非常に効果的です。相続税は原則として現金一括納付が必要となるため、納税資金を準備しておかなければなりませんが、生命保険を上手に活用すれば、大切な資産を手放すことなく相続税が納付できるでしょう。
相続税対策で注意すべき落とし穴

相続税対策を進める上で、後々問題となりやすい点には注意が必要です。税務署からの指摘や、相続人間でのトラブルを避けるために、注意すべき重要なポイントについて解説します。
税務調査で指摘されやすいポイント
税務調査では、名義預金、生前贈与、不動産の評価などが重点的にチェックされます。名義預金とは、被相続人名義ではないものの実質的に被相続人の財産とみなされる預金で、資金の流れや管理状況から判断されます。
また、生前贈与は、贈与の事実や財産の移転が不明確だと否認される可能性があります。さらに、不動産の評価は、複雑な計算が必要なため、単純ミスなどから過小評価と判断される場合も珍しくありません。
これらの点に不備があると、追徴課税や加算税などのリスクが生じてしまいます。そのため、これらに該当する場合、できるだけ早い段階から専門家である税理士に相談しておくと良いでしょう。
家族内トラブルを防ぐために
遺産分割を巡る親族間の対立は、相続において深刻な問題です。これを防ぐためには、被相続人の意思を明確にする遺言書の作成が非常に有効です。遺言書があれば、相続人間の無用な争いを避けることができます。また、生前に相続財産や分け方について家族で話し合っておくことも大切です。お互いの意向を理解しておけば、相続発生後の紛争を予防できます。
もし、話し合いが難しい状況であれば、弁護士などの専門家に早めに相談し、適切なアドバイスを受けると良いでしょう。
まとめ
本記事では、3億円の相続税について、詳細なシミュレーションと、最新の税制を踏まえた節税対策を解説しました。相続税は、事前の準備と対策によって、その負担を大きく軽減することが可能です。今回の情報を参考に、早めに専門家へ相談し、ご自身の状況に合わせた相続対策を始めるようにしましょう。