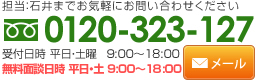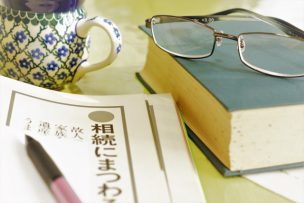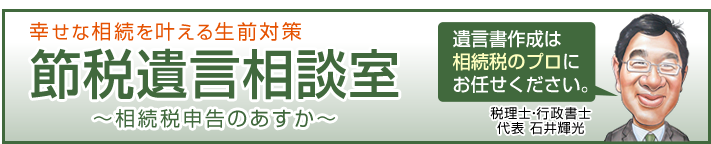souzoku-station
souzoku-station
子や孫が住宅を建てるための資金を生前贈与すると、将来の相続財産が減るため相続税の節税をすることが出来ます。また贈与された子や孫は、住宅ローンを組まずに念願のマイホームを手にすることが出来ます。
このように生前贈与した資金で住宅を建てる場合、贈与する側もされる側も、どちらにとっても良いこと尽くめになるわけですが、一方では制約や気を付ける点も多く、やり方を間違えると最悪の場合、高額の贈与税を支払うことになってしまうので注意が必要です。
そこで今回は、生前贈与した資金で住宅を建てる際に知っておきたいポイントや注意点などについて解説していきます。